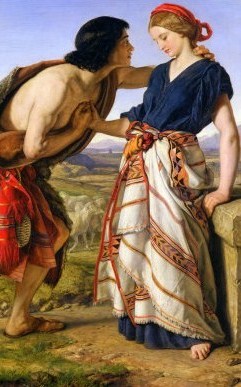はじめに
辻邦生「ある告別」を久々に読みました。試験勉強もあって最近は実学の本しか読んでいませんでしたので、辻ワールドの甘美さに心打たれて、ショックが強すぎです。会社勤めには辛いです。
辻 邦生
講談社
売り上げランキング: 860460
この作品がちゃんと分かるようになったのは、おそらく30代になってからです。10代、20代のころは全く分かりませんでした。それは至極当然で、なぜなら、この作品のテーマのひとつが「喪われた若さと以下に訣別するか」だからです。
若さを喪わないとこの作品の価値が分からないというのは、私の想像力不足なんで、いまいちなんですけどね。
この作品の魅力
「若さと見事に訣別したものだけが、永遠の若さを造形することが出来る」
これがこの作品の中で示される最も大きなテーマのように思います。
これは歳を重ねようとも、若さの中に生き続けようとする処世術のようなものを感じると、すこし穿った見方になってしまいそうです。
そうではなくて、おそらくはこの作品は、辻邦生の文学宣言のひとつなのでしょう。
最後に綴られる以下の文章に、
「こんどは、彼女たちの映像にみちた世界への旅立ち」
という一節をみると、この「彼女たちの映像」というのが、文学世界において永遠の若さというイデアールな概念を体現していこうという、意気込みのように感じるのです。
ちなみに「映像」には傍点がふられていますので、何かしらの意味を見て取るのが普通だと思います。
辻文学全体における位置づけ
これは何度も書いているように辻邦生の原初体験というのが3つあるのですが、この作品に描かれるパルテノン神殿との邂逅がその1つめの原初体験に当たります。この邂逅において、辻邦生は「美が世界を支える」という直観に到達します。
ですが、個の作品においては、パルテノン神殿との邂逅については深く言及されることはありません。ただ「どうしてこんなものが地上にありうるのか。どうしてだろう。どうしてだろう」という一文があって、そのあとに、それが何かの啓示なのだろうが、何かは分からない、と書かれています。
個の作品の主人公はおそらくは辻邦生本人だと思いますので、素直に読めば、この時点では「美が世界を支える」という直観に到達せず、徐々に醸成されていったものだったといえるでしょう。
ただ、ここで手の内をすべて飽かすと、若さに関する主題が弱くなるので、あえて隠蔽しているともとれますが。
終わりに
最近、いわゆる小節をあまり読んでいませんでした。なんだか小節なんてあまりに浮世離れしている、とおもったからです。
ですが、時には立ち止まってみないとなあ、と思います。
また、辻邦生を読みはじめないとなあ、と思います。